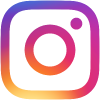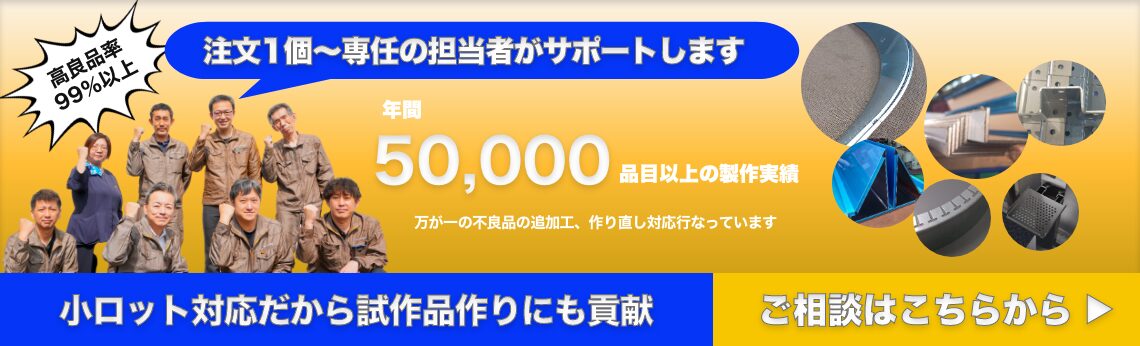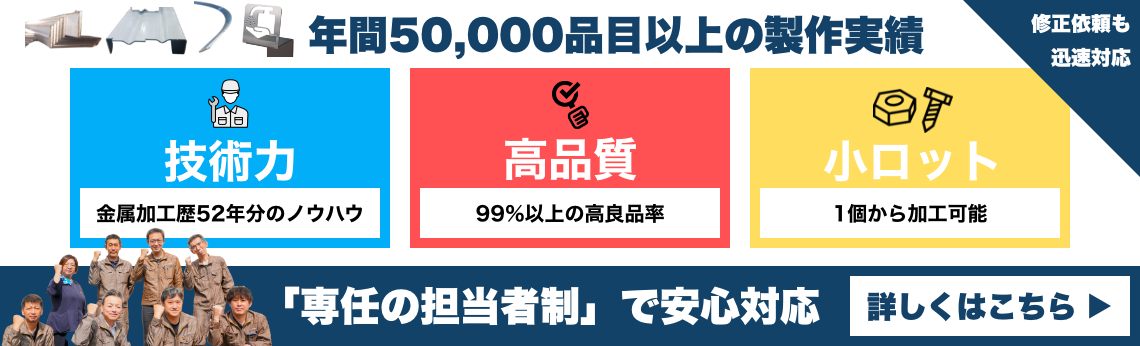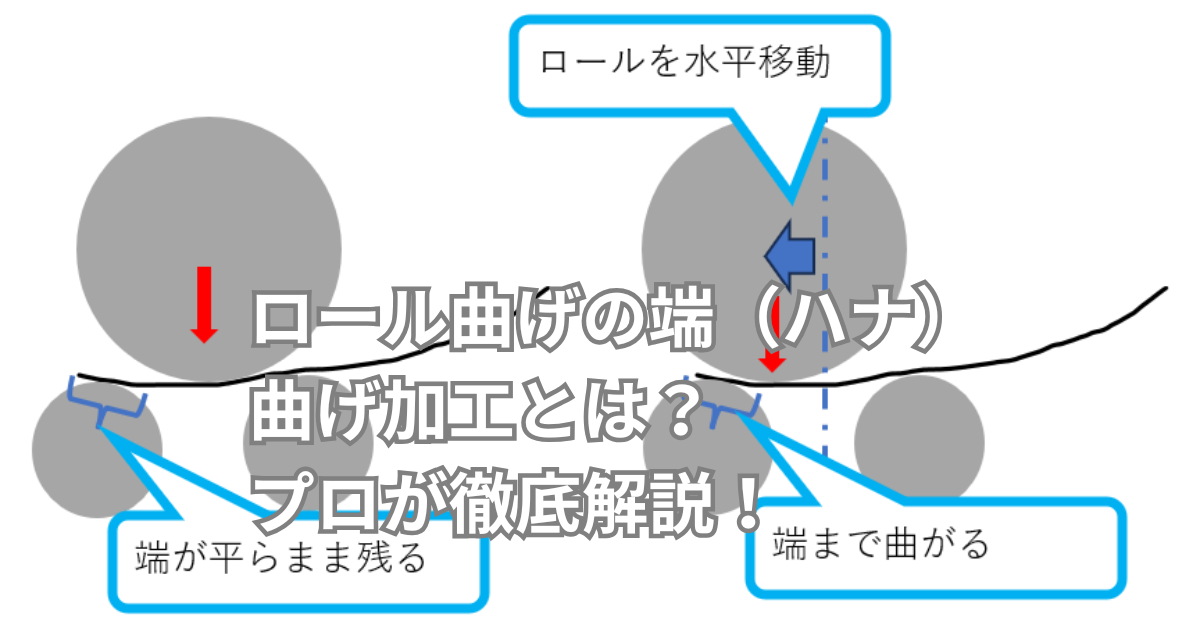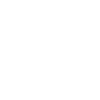「溶接のコストをできるだけ抑えたい」
「そもそもこの部品、溶接できる?」
設計をしていくと、どうしても溶接が必要な場面が出てきますよね。
溶接は切り・曲げに比べてハードルが高いと感じている若手技術者が多いように感じます。
その理由は、溶接のバリエーションの多さにあると考えています。
しかし、裏を返せば何でも溶接できるようになってきた、とも言えます。
今回は金属加工実績50年の当社が、できるだけわかりやすく溶接技術について解説します。
この記事を読めば溶接の基本的な内容と、コストを抑えるコツが分かるようになります。
メーカー出身社員の話も取り入れた、設計者目線の内容になっています。
肩の力を抜いて、ぜひ最後まで読んでいってください。
金属加工のご相談はお気軽にリョーユウ工業まで!
>>「ご相談・見積り」
溶接加工とは

溶接とは。
JISの定義を抑えておきましょう。
「2個以上の母材を、接合される母材間に連続性があるように、熱、圧力またはその両方で一体にする操作」
(引用:JIS Z3001-1:2018)
つまりは溶(とかして)、接(つなげる)。
言葉の通りです。
溶接はさらに、金属溶接、プラスチック溶接に分類できます。
今回扱うテーマは金属溶接です。
(この記事では以降、溶接加工と呼びます)
溶接加工の大きな目的は部品間の連結強度を高めたり、一体化させたりすることです。
「部分的に補強したい」
「一体化させて、組み立てプロセスを簡単にしたい」
こんなシーンで溶接は使われます。
溶接は今や、製造業や建設業など、さまざまな分野で欠かせない技術となっています。
周りを見渡してみれば、橋梁やビルの骨組み、機械のフレーム、自動車のボディなど、多くの構造物や製品に溶接が活用されていることが分かると思います。
近年では、ロボットによる自動溶接やレーザー溶接といった高度な技術も導入されており、より精密かつ効率的な加工が可能になってきました。
溶接加工の種類
アーク溶接
最も一般的な溶接方法です。
電気アークによって発生する高温で金属を溶かし、接合します。
設備コストが安価で操作もシンプルなため、多くの現場で採用されています。
鉄やステンレスなど幅広い金属に対応でき、建築や製造業など幅広い分野で活用されている万能な溶接方法です。
TIG溶接(アルゴン溶接)
高品質な仕上がりが求められる場面で使用される溶接方法です。
(TIG溶接:Tungsten Insert Gas溶接の略)
非鉄金属や薄板の加工に向いており、特にアルミニウムやステンレスの溶接で多く用いられます。
ただし、職人の技術が要求されるため、コストは高くなる傾向があります。
MIG溶接
TIG溶接よりも安価に加工できる溶接方法です。
(MIG溶接:Metal Insert Gas溶接の略)
半自動溶接とも呼ばれ、作業効率が高く量産に向いています。
アルミやステンレスにも対応可能で、建築や機械部品の製造などで利用されています。
レーザー溶接
高出力レーザーを用いて金属を瞬時に溶かし、接合する溶接方法です。
精密かつ高速に加工できるという特徴があります。
熱による歪みが少ないため、美観が重視される製品や微細な部品の加工に適しています。
ただし、専用設備が高額なため、導入コストや加工単価は比較的高くなる傾向があります。
抵抗溶接
スポット溶接とも呼ばれ、金属同士を電流の抵抗熱で接合する溶接方法です。
自動車や電化製品の薄板溶接に多く使われます。
溶接加工について詳しく知りたい方は、こちらの記事が参考になります。
>>「金属加工|溶接の種類とは?溶接方法から欠陥事例まで5分で解説!」
材料の種類や精度、美観、予算などに応じて最適な溶接方法というのは変わってきます。
経験を積まないと中々わかりづらい分野ですよね。
わからないことがあれば、ぜひ当社を利用してください。
経験豊富なスタッフが誠実、丁寧にお答えいたします!
溶接加工の見積もりはどうやって決まる?
材料費
材料費は使用する金属の材料、サイズや板厚、発注数量によって変わります。
| 材料 | 鋼材はアルミやステンレスなどは鋼材と比べると安価です |
| サイズ | 切り出す前の原板はサイズが決まっています。 取り数が悪くなると(ロスが多くなると)高価になります |
| 板厚 | 薄板や流通量の多い板厚材料は安価です |
| 数量 | まとめ発注により材料費を抑えられます |
加工費
溶接の種類や材料の種類によって使用する設備、加工難易度が変わるため価格が変動します。
例えば、精密なTIG溶接やレーザー溶接、曲線部の溶接などは高価になります。
基本的には、抵抗溶接→MIG溶接→TIG溶接→レーザー溶接の順に加工費は上がると考えて問題ありません。
部品に求める強度や精度、仕上がり品質などに応じて加工方法を選択すると良いでしょう。
人件費
人件費は作業にかかる時間と作業者の時間単価によって決まります。
溶接の範囲が広い場合、厚板の場合は、作業時間が増加するため人件費が上がります。
加工が難しい材料(アルミやチタンなど)や形状が複雑な場合は、高度な技術が求められるため、時間単価が上がり、人件費もさらに高くなります。
設計段階で材料や形状を意識することがコスト抑制の鍵と言えます。
その他経費
専用のジグを使う必要がある場合は、ジグの制作費が加算されるため注意が必要です。
また、発注数量が少ない場合、各工程のセッティングや検査費、保管費、運送費負担が大きくなるため割高になります。
(極端に言えば、1個作っても100個作っても同じだけの経費がかかるためです)
これらを念頭に置き、複数社に見積もりを依頼、明細を比較・検討することで相場感が掴めるようになってきます。
当社は創業以来、透明性の高い見積もりと、ご希望に寄り添った対応で信頼を積み上げてきました。
お客様のビジネスは私たちのビジネスです。
お仕事のご依頼、お待ちしております!
溶接加工の見積もりの流れ

1|図面・仕様書の準備
見積もりを依頼する前に、部品のサイズ、形状、材質、必要な精度などを記載した図面や仕様書を準備しましょう。
CADデータがあると、業者側が部品形状や寸法を正確に把握でき、見積もりの精度が高まります。
手書きのポンチ絵でも問題ないですが、寸法や溶接箇所の指示が明確になっていることが重要です。
完璧な図面である必要はありません。
あまり気負わず準備しましょう。
2| 見積もり依頼(複数社)
メールやWebフォームを通じて業者に見積もりを依頼しましょう。
このとき、必要数量、希望納期、希望予算といった条件も一緒に伝えます。
部品の使用用途や注意すべきポイントを併せて業者に伝えておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
図面上に記載してしまっても構いません。
伝え忘れや「言った、言わない」を回避できるため、おすすめです!
3|打ち合わせ(必要な場合)
図面や仕様書だけではわからない点や、加工に伴う懸念事項がある場合は、業者から確認の連絡がある場合があります。
曖昧な点はこの時点で解消しましょう。
些細なことでも、コミュニケーションを取っておけば「こんなはずでは・・・」という最悪の事態を回避できます。
実は加工トラブルの多くは設計者側の「言わなくても汲み取ってくれると思った」、加工業者側の「そんなに重要な箇所だとは思わなかった」というコミュニケーション不足に起因するケースが非常に多いのです。
面倒な作業ですが、できるだけ設計意図の共有を心がけましょう。
4| 見積りの比較
加工業者から見積もりが来たら、明細を比較・検討しましょう。
<チェックポイント>
・材料費、加工費、人件費の明細が載っているか
・極端に高い、安い項目がないか
・打ち合わせや問い合わせのレスポンス、応対はスムーズだったか
・懸念事項を把握・伝達しているか
・納期は適切か
総合的に判断し、信用できると思った依頼先を選ぶことが重要です。
とはいえ、価格が最重要、早さ優先といった状況や事情もあるかと思います。
「開発日程がタイトで・・・」
「予算が絞られてて・・・」
こんな状況はよくありますよね(汗)
依頼する部品の重要度や、リスク許容度に応じて依頼先を検討・決定すればOKです。
5| 発注
条件が合えば正式に発注を行いましょう。
発注後は最低でも1回は業者と進捗確認を行い、コミュニケーションを取ると良いと思います。
関係構築をしておくと、納品まで、さらには次回以降の仕事がスムーズに進むためです。
当社のお客様にリピーターが多いのは、そうしたメリットを感じていただいているからだと考えています。
絶対に損はさせません。笑
コスト削減のポイント
最後に豆知識として、溶接加工のコスト削減のコツをいくつかご紹介します。
とにかく形状はシンプルに
設計者は限られた制約の中で、機能を満たす部品を設計する必要があります。
そのため、なんとか1つの部品で実現できないかと頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。
しかし、「形状はシンプルに」がコストを抑えるコツなのです。
・形状がシンプルであれば、部品点数は増えても、部品代は安く、加工費も安く、組み立て品質は安定し、トラブルが減ります。
・形状が複雑であれば、部品点数は少なくても、部品代は高く、加工費も高く、組み立て品質は安定せず、トラブルが増えます。
このトラブルの種が下流工程、最悪の場合は市場で不良という形で発生してしまった場合の損失は計り知れません。
シンプルで必要な機能を満たした部品には、機能美と呼べる美しさがあります。
長年、金属加工に携わってきて感じることは結局、「シンプル is ベスト」なのです。
鋼材で設計する
鋼材は強度が高い上に、材料費が安価、かつ加工もしやすい材料です。
こんな万能な材料を、敢えて使わないという選択肢はありません。
鋼材の欠点が致命的な場合にのみ、他の材料を検討するようにしましょう。
<鋼材の欠点>
・重い
・錆びやすい
・熱伝導率が低い
鋼材の欠点を解消してくれた金属が軽いアルミであり、錆びにくいステンレスであり、熱伝導率の高い銅だったわけです。
金属加工の歴史は鋼材加工の歴史だったと言っても過言ではないほど、あらゆる加工技術が確立されています。
どんな時も「鋼材ではダメなのか?」という視点を持ことが重要です。
一貫対応の業者を選ぶ
金属加工業者の中には切り・曲げを専門にしている業者や、溶接を売りにしている業者もあります。
当社のように切り・曲げから溶接、表面処理まで一貫して行っている業者もあります。
<専門業者を使うメリット>
・加工スピードが速い
・単工程のため見積もりがシンプル
・単工程のためコストが安い
<一貫業者を使うメリット>
・複数行程の場合はコストが安い
・品質責任の所在が明確
・手間が少ない
部品の溶接加工を依頼する場合、溶接だけを依頼したいというケースは少ないのではないでしょうか。
おそらく溶接を含む部品の切り・曲げ加工を同時に依頼される方が多いと思います。
複数の工程を同時に依頼する場合は、一貫業者に依頼をおすすめします。
理由は工程間を分断せず、まとめて依頼できるメリットが大きいからです。(安い、品質安定、手間が減る)
当社は金属加工のことならほとんど扱っている、一貫対応の会社です。
金属のことなら何でもお任せください!
業者に事前相談する
設計段階で早めに加工業者へ相談しておくと、後戻り作業が減るため、効率的に開発を進められます。
簡単な部品や、過去に採用経験のある形状であれば、わざわざ時間をかけて業者と話をする必要はありません。
しかし、ご自身で設計をしていて「ん?大丈夫か?」「あまり見ない形状になってしまった」といったご経験はないでしょうか。
違和感を感じたら、信用できる業者に相談してみてください。
早い段階で、思わぬ落とし穴が見つかるかもしれません。
<加工業者の回答例>
・加工の保証はできない(やってみないと分からない)
・加工はできるが、精度はばらつく(それでも問題ない部品か)
・問題なく加工できる
こうした加工業者側の回答を参考に、設計段階で打てる手を打っておくと、後戻り作業が減ります。
部品の重要度と開発日程、ご予算と照らし合わせ、総合的に判断していきましょう。
まとめ
今回は溶接加工の見積もりの基本と、コスト削減のコツというテーマでお話をしました。
<要点>
・溶接加工の目的は「強度アップ」「一体化」
・「抵抗溶接(スポット溶接)」→「MIG溶接」→「TIG溶接」→「レーザー溶接」の順に高品質、高価になる
・コスト削減のコツは「①シンプル形状」「②鋼材を使う」「③一貫業者に依頼」
溶接加工の基本を正しく理解することは、コストを抑えつつ、質の良い部品を作るために不可欠です。
信用できる業者を見つけて、設計段階から一緒になって開発を進めていきましょう。
溶接加工の見積もり、問い合わせはお気軽にリョーユウ工業まで!
金属加工の豆知識一覧に戻る